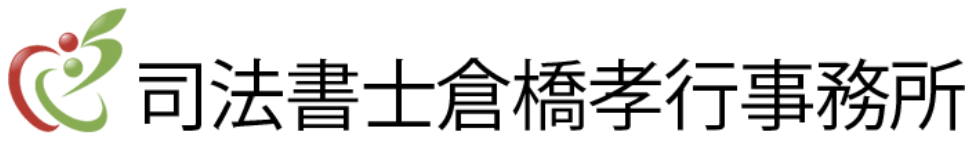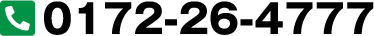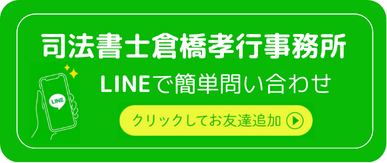自分でできる相続登記1 戸籍を読む
〜実務の現場から見る、戸籍の取得と読み方〜
1.自分でできる相続登記の趣旨
この記事では、相続登記を自分で行うための実務的手順を、現場の視点から解説します。
法的な理論や学術的な議論よりも、実際に役所や法務局でどのように進めるかという「現場の流れ」に重きを置いています。
したがって、内容の一部は厳密な法律論とは異なる場合もありますが、現場で通用する実践的な手引きとしてお読みください。
相続登記の連載の第1回目となる今回は、最初のステップである**「戸籍を読む」**ことをテーマに説明します。
2.戸籍を取得する
ここで言う「戸籍」とは、戸籍・除籍・改製原戸籍のすべてを含みます。
初めての方は、細かい違いを今理解しようとしなくても構いません。まずは流れをつかみましょう。
被相続人の戸籍を取得する
被相続人とは、相続の対象となる亡くなった方のことです。
たとえば「父が亡くなった場合」、父が被相続人になります。
被相続人の戸籍は、その方の本籍地の市区町村役場で取得します。
窓口で次のように伝えるとスムーズです。
「被相続人〇〇〇〇の出生から死亡までの戸籍をください。」
これで、必要な戸籍一式(改製原戸籍、除籍、現行戸籍)が発行されます。
併せて、**戸籍の附票(住所の履歴)**を取得しておくと便利です。
附票があると、住所の移転や相続登記時の確認がスムーズになります。
もし被相続人の本籍地と不動産の所在地が同じ市町村であれば、ついでに固定資産評価証明書も取得しておきましょう。これは登記の登録免許税の算定に必要な書類です。
まとめ:役場で取得すべき書類
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(現戸籍・除籍・改製原戸籍)
- 被相続人の戸籍の附票
- 固定資産評価証明書(同一役場で取得可能な場合)
3.戸籍の種類と基礎知識
3-1 戸籍の様式の沿革
戸籍には、明治初期から数種類の様式(壬申戸籍、明治19年式、明治31年式、大正4年式など)があります。
ただし、相続登記の実務では、この違いを詳しく理解する必要はほとんどありません。
どの様式であっても、出生から死亡までの連続性を確認することが重要です。
3-2 戸籍・関連書類の種類と意味
相続登記で使う書類には、以下のような種類があります。
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 戸籍 | 家族関係・身分事項を記録した基本台帳。婚姻・出生・死亡などの情報が記載。 |
| 除籍 | 戸籍内の全員が死亡・転籍などで抜けた状態。もう更新されない戸籍。 |
| 改製原戸籍 | 法改正による様式変更の前の戸籍。除籍と同じく更新停止。 |
| 戸籍の附票 | 戸籍上の全員の住所履歴を記録。登記時の住所確認に使用。 |
| 除票 | 転出・死亡で消除された住民票。 |
| 固定資産評価証明書 | 不動産の評価額が記載される。登録免許税計算に使用。 |
| 印鑑証明書 | 実印が登録されていることを証明する。遺産分割協議書に添付。 |
これらのうち、「戸籍」「除籍」「改製原戸籍」の3つが被相続人の身分関係をたどるうえでの主役です。
4.戸籍の読み方
戸籍を読む目的は、被相続人の一生を通して家族関係がどう変化したかを理解することです。
つまり、「どの戸籍に生まれ」「どの戸籍で終わったか」を確認します。
この流れがつながれば、出生から死亡までの戸籍を正しく収集できていることになります。
4-1.戦前の戸籍を読むポイント
戦前の戸籍(旧民法時代)は、家制度(戸主・家督相続)に基づいて編製されています。
読む際のコツは、「いつ戸籍が作られ、いつ消滅したか」を探すことです。
- 戸主欄の右側から左へ読み進める
- 「家督相続」「分家」「転籍」などの文字があれば、それが編製の原因と年月日
- さらに左へ進み、「家督相続」「転籍」「改製」などがあれば、それが除籍・原戸籍の原因と年月日
この2つの年月日の間が戸籍の存続期間です。
この期間を押さえることで、被相続人の在籍期間や身分変動を把握できます。
4-2.戦後の戸籍を読むポイント
戦後の戸籍(昭和23年以降)は、用紙上部に**「編製事由および年月日」**が明記されています。
また、除籍・改製の年月日も欄外または下段に記載されており、視覚的に理解しやすい構成です。
これを確認するだけで、「いつ作られ、いつ終わった戸籍か」がすぐに判断できます。
4-3.被相続人の身分事項を確認する
戸籍には、被相続人の出生・婚姻・離婚・養子縁組・離縁・死亡などの「身分事項」が記載されています。
これらの身分事項を読み取ることで、
- どの戸籍に移ったのか
- 誰と婚姻・離縁したのか
- いつ死亡したのか
が明らかになります。
たとえば「○年○月○日 死亡により除籍」と記載があれば、その戸籍が最終のものです。
「除籍になる」という言葉は、「戸籍の中の特定の人物が抜ける」場合にも使われ、
「戸籍そのものが除籍になる(全員抜ける)」とは異なります。
この点を混同しないよう注意が必要です。
4-4.総括:戸籍の流れを「一本の線」で見る
被相続人の戸籍をすべて揃えたら、その人の一生分の戸籍が途切れずつながっているかを確認します。
- いつ生まれたか(出生)
- いつ婚姻し、どの戸籍に移ったか
- 最終的にどの戸籍で死亡したか
この3点が明確にわかれば、戸籍を正しく読めたことになります。
相続登記の第一歩はここまでで完了です。
次のステップは、**「相続人の確定」**です。
被相続人の一生分の戸籍を読み終えたあと、誰が法定相続人になるかを判断していきます(次回の記事で詳しく解説します)。
まとめ:戸籍を読めるようになると相続登記は怖くない
相続登記の第一歩は、「被相続人の戸籍をきちんと揃えること」。
そして、その戸籍の「始まりと終わり」を理解することです。
この作業ができれば、相続関係説明図の作成や登記申請書の準備も格段にスムーズになります。
最初は難しく感じても、戸籍を読み慣れると、
家族の歴史が一本の線のように見えてくるはずです。