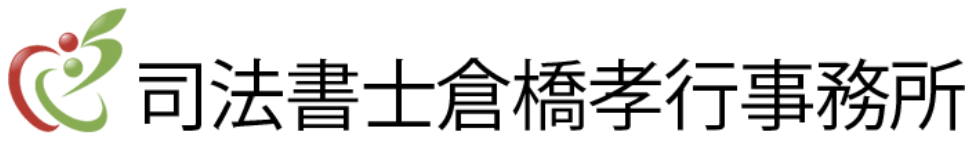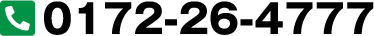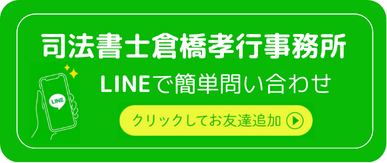遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった方)が残した遺産を、相続人同士でどのように分けるかを話し合って決める手続きです。
遺言書がある場合は基本的にその内容に従って相続が行われますが、遺言書がない場合、または一部の財産しか記載されていない場合には、
法定相続人全員で協議を行う必要があります。
この協議によって相続人全員が合意すれば、「遺産分割協議書」という書面を作成し、それぞれが署名・実印を押印します。
遺産分割協議書は、不動産の登記変更や銀行口座の名義変更など、遺産を正式に各相続人へ引き渡すための重要な証拠となります。
なお、遺産分割協議は、被相続人が亡くなった後、いつでも始められますが、
相続税の申告期限(原則として死亡から10ヶ月以内)を考慮すると、早めの対応が望ましいです。
遺産分割協議の手順
遺産分割協議は、以下のようなステップで行われます。
1. 相続人の確定
まず最初にすべきことは、法定相続人を正確に把握することです。これには被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を収集し、
法律上の相続人(配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹など)を確定する必要があります。
養子や認知された子など、戸籍上見落としがちな相続人もいるため、丁寧な確認が求められます。
2. 相続財産の調査
次に、被相続人が所有していた財産を調査します。これは正の財産(不動産、預貯金、株式、車など)だけでなく、
負の財産(借金、ローン、保証債務など)も含まれます。
3. 相続財産の評価
調査した財産に対して、時価ベースで評価を行います。これにより、相続人間で公平な分割を検討しやすくなります。
特に不動産や非上場株式などは評価が難しいため、必要に応じて不動産鑑定士や税理士の助言を受けましょう。
4. 分割方法の協議
相続人全員が一堂に会するか、書面や代理人を通じて話し合い、どの財産を誰がどのように取得するかを協議します。
この段階で感情的な対立が生じることもあるため、冷静な話し合いと専門家の関与が重要です。
5. 遺産分割協議書の作成
協議内容がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。これは以下の要素を含む必要があります:
- 相続人全員の署名・実印
- 相続財産の明細とその分配方法
- 相続人の住所・氏名
- 印鑑証明書の添付(不動産登記などで必要)
6. 名義変更・登記手続き
協議書に基づいて、不動産、銀行口座、自動車などの名義変更を行います。これには各機関への申請が必要で、
それぞれの書類・手数料・手続きの期限が異なるため注意が必要です。
遺産分割の4つの種類
1. 現物分割
財産をそのままの形で分ける方法です(例:長男が不動産、次男が預金)。
メリットは手続きがシンプルであることですが、財産の価値に差があると不公平感が生まれやすいです。
2. 換価分割
財産を売却して現金化し、その現金を相続人で分ける方法です。不動産など分けにくい資産に適しており、
公平な分配がしやすい反面、売却まで時間がかかることもあります。
3. 代償分割
一人の相続人が財産を取得し、他の相続人に代償金を支払う方法です。
例えば、長男が実家を相続し、兄弟に現金で補填するなどです。代償金を準備できるかがポイントとなります。
4. 共有分割
相続人が共同で財産を共有する方法です(例:土地を兄弟で共有名義にする)。
当面の対立は避けられますが、将来的に売却や処分をめぐってトラブルになることもあります。
遺産分割協議が不成立の場合
相続人全員の合意が得られず、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。
裁判所の調停委員が間に入り、話し合いが進められます。
調停でも合意に至らない場合は、「審判」という手続きに移行し、裁判官が遺産の分割方法を決定します。
いずれの手続きも時間と費用がかかるため、可能な限り協議の段階で解決するのが理想的です。
遺産分割を行う際の注意点
- 相続人全員の参加が必須:1人でも欠けた協議は無効です。
- 遺留分の配慮:一部の法定相続人には最低限の取り分が法律で保障されています。
- 税務手続きの期限:相続税の申告と納付は、原則として相続開始から10ヶ月以内に行う必要があります。
- 専門家の活用:弁護士や司法書士、税理士のサポートを受けることで、円滑な協議・手続きが可能になります。