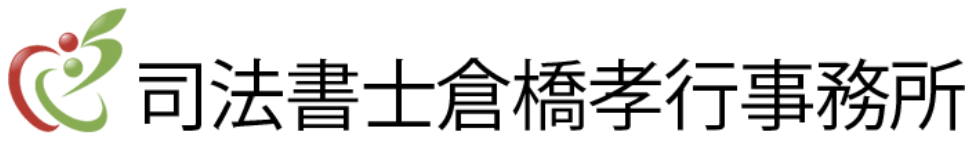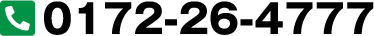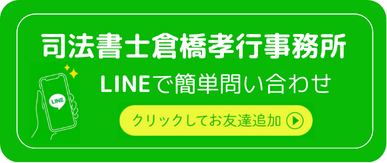相続と調査
1. 相続財産の全体像を把握するための基本ステップ
相続が発生すると、まず行わなければならないのが「財産の全体像の把握」です。何をどれだけ遺したのか、正確に知ることはすべての相続手続きの出発点となります。
この段階で調査すべき財産は、現金や預貯金、不動産、株式・投資信託などの有価証券、自動車や貴金属などの動産、生命保険や死亡退職金なども含まれます。また、プラスの財産だけでなく借金やローン、保証債務といったマイナスの財産も対象です。
以下のステップを踏むことで、全体像を的確に把握することが可能です。
- 手元にある通帳、証書、契約書類、保険証券などを確認
- 家の中や貸金庫に残された書類の整理
- 金融機関への問い合わせや残高証明の取得
- 不動産登記簿の調査や名寄帳の請求
- 借入金・ローンの存在確認
2. なぜ財産の洗い出しが相続の初期段階で不可欠なのか
2-1. 遺産の分け方を決める前提として必要
遺産分割協議を行うには、遺産の内容が明らかになっている必要があります。不動産がどこにあるか、預金がいくらか、他の資産が何か分からないまま協議をしても、後に新たな財産が判明した場合、やり直しやトラブルの原因になります。
2-2. 相続を受けるか放棄するかを見極める材料になる
相続は単に受け取るだけのものではなく、負債を含めた財産全体を引き継ぐ「包括承継」です。そのため、借金が多い場合などは「相続放棄」や「限定承認」を選択する判断が必要であり、その材料となるのが財産調査の結果です。
2-3. 相続内容を正確にするために重要
相続は、すべての財産を網羅しなければなりません。相続税の課税対象である場合、財産を把握していなければ過少申告となり、加算税や延滞税の対象となる可能性があります。調査を怠ることはリスクにもつながります。
3. 相続財産の調査はなぜ早急に行うべきなのか|死亡後2ヶ月の目安
相続放棄や限定承認の申述には「自己のために相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という民法上の期限(熟慮期間)があります。そのため、遅くとも死亡後2ヶ月以内にはおおよその財産状況を把握しておくことが望まれます。
また、相続税の会税対象である場合、相続税の申告は原則として死亡から10ヶ月以内。複数の専門家に関与してもらう場合もあるため、早めの財産調査がタイムマネジメントの上でも重要になります。
4. 財産調査は自分でできる?
財産調査は相続人自身でも可能です。財産調査は以下のようなケースがあります。場合によっては、弁護士などの専門家に頼む必要がある場合もありますが、司法書士の場合、財産調査については助言サポートが業務の範囲内となっております。お客様自身の財産調査についてアドバイスしたりやり方をお知らせしたりすることが主な業務となります。
- 被相続人が複数の金融機関や証券会社と取引していた
- 不動産が広範囲にわたっている
- 借金や保証債務があるか不明
- 海外に資産や相続人がいる
- 時間的余裕がない、調査に不安がある
専門家に依頼相談することで、漏れやミスを防ぎ、効率的な財産調査が可能となります。
5. 【ご自身で調査する場合】資産ごとの調査の具体的方法
5-1. 預金口座を調べる際の実務手順
通帳やキャッシュカードをもとに、取引のあった金融機関へ「残高証明書」や「取引明細書」を請求します。解約手続きは相続人全員の同意が必要なため、まずは調査段階として問い合わせ・照会が基本です。
5-2. 借入金やローンの有無を確認する方法
ローン契約書や督促状、クレジットカード利用明細が残っていないか確認します。信用情報機関(CIC・JICC)への開示請求も有効です。保証人となっていた場合も注意が必要です。
5-3. 不動産の所有状況を調査する手順
被相続人の住民票のあった市区町村で「名寄帳」を取得することで、名義人としての不動産を一括で確認できます。また、法務局で「登記簿謄本(登記事項証明書)」を取得して詳細情報を確認します。
5-4. 株式・投資信託・債券など金融資産の確認方法
証券会社の口座番号や取引履歴が分かれば、残高証明書や取引明細の発行を依頼できます。特にネット証券の場合、ID・パスワードの管理状況にも注意が必要です。
6. 【漏れ防止の工夫】個人で財産調査を進めるためのポイント集
6-1. 調査は資産の種類ごとに優先順位をつけて進める
預金・不動産・負債のように、相続への影響が大きい順に優先度をつけることで効率的な調査が可能になります。
6-2. 通帳・証書・登記簿などの保管場所をチェック
保険証券、印鑑証明、契約書などがまとまって保管されている「書類ボックス」や貸金庫、押入れ・引き出しなどのチェックも欠かせません。
6-3. 調査結果は財産一覧表(目録)としてまとめる
調査した内容を「相続財産目録」として一覧にしておくことで、遺産分割協議や税務申告、金融機関での手続きがスムーズになります。できればエクセル等でデータ化しておくと管理もしやすくなります。
7. 相続人の確定調査も必要
7-1. 相続人を誤ると遺産分割が無効になる可能性がある
すべての相続人が関与していない協議は法的に無効とされるため、相続人の確定は極めて重要です。
7-2. 戸籍の収集は出生から死亡までをすべてたどる必要がある
戸籍調査では「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍」を集める必要があります。改製原戸籍や除籍謄本も対象となり、複数の市町村をまたぐこともしばしばあります。
7-3. 相続人が行方不明・海外在住の場合の対応方法
家庭裁判所で「不在者財産管理人」や「特別代理人」の選任を申立てる必要があります。海外在住者との連絡・委任状の取得にも時間がかかるため、早めの着手が必要です。
7-4. 家系が複雑な場合や再婚・養子縁組がある場合の注意点
相続人の中に前妻の子がいる、養子縁組がある、認知された子がいるなど、家族関係が複雑な場合には、戸籍の精査が重要です。思わぬ相続人の存在が判明することもあります。
7-5. 法定相続情報一覧図を活用するとその後の手続きがスムーズ
確定した相続人をもとに「法定相続情報一覧図」を作成すると、複数の機関に同じ戸籍を何度も提出する手間を省けます。司法書士が代理申請を行うことも可能です。
8. 専門家に依頼するなら誰に?それぞれの専門性と適材適所
- 司法書士: 相続登記や法定相続情報一覧図の作成、戸籍調査のプロフェッショナル。
- 税理士: 相続税の申告、財産評価、不動産の路線価算出などに強い。
- 弁護士: 相続人間の紛争や訴訟、遺留分侵害などへの対応に必要。
- 行政書士: 各種書類作成や許認可、補助金等に関する手続き支援。
財産調査だけでなく、今後の手続き全体を見据えて、誰に何を依頼すべきか見極めることが大切です。