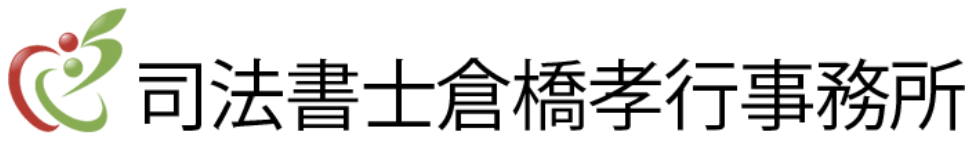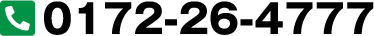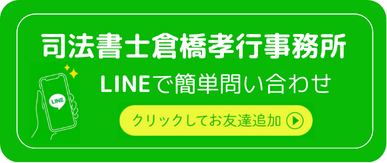相続と空き家
1. 相続によって空き家を所有するケースが多数を占める背景
日本では少子高齢化と都市集中型の社会構造が進行しており、地方部を中心に住宅の空き家が深刻な問題となっています。特に「相続」をきっかけに発生する空き家の割合は非常に高く、国土交通省の調査によれば、その原因の約半数以上が相続に起因しているとされています。これは、親世代が所有していた住宅を、子世代が使用しないまま引き継いだ結果です。特に、都市部に生活拠点を持つ子どもたちが地方の実家を使う予定もなく、そのまま空き家として放置してしまうことが多いのです。
さらに、戦後の持ち家志向や不動産信仰の強さから、1世代上が所有していた不動産が相続によって次の世代へと引き継がれるケースが一般的です。しかし、人口減少と地方過疎化が進行する中では、それらの住宅を「活用する」ことが現実的に困難であるため、結果として空き家のまま放置されてしまいます。
1-1. 空き家の相続は義務なのか?法的な位置づけ
相続は「権利」であり「義務」ではありません。民法上、相続人には相続するか放棄するかの選択肢があります。ただし、放棄する場合には原則として相続の開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をしなければなりません。この期間を過ぎると、単純承認(すべての遺産と負債を受け継ぐ)とみなされ、空き家を含む全財産の相続が確定してしまいます。
また、相続放棄の意向があっても、放棄の申述を行う前に空き家の管理や修繕などを行うと、相続を承認したと見なされる場合があります。したがって、相続を希望しない場合には、何も手を加えず、速やかに法的手続きを行う必要があります。
2. 空き家の相続を回避したいと考える前に知っておきたいこと
空き家の相続を避けたいと考える理由の多くは、管理の手間や維持費、固定資産税の負担、近隣とのトラブルなどですが、単純に放棄すれば済むというものではありません。相続放棄にはさまざまな制約や副作用があります。
2-1. 相続放棄には他の財産の放棄も伴う点に注意
相続放棄は「すべての相続財産を受け取らない」という法的効力を持ちます。空き家だけを選択的に放棄することはできず、預貯金や有価証券、自動車、現金といったプラスの財産も一切受け取ることができなくなります。特に、資産内容が不明確なまま放棄してしまうと、結果として損失を被る可能性もあるため、必ず遺産全体を調査したうえで判断する必要があります。
2-2. 放棄後も管理責任が問われる可能性について
相続放棄をしても、次の相続人が相続するまでの間、空き家の管理責任は「現実にその家を管理できる立場にある人」が担う場合があります。たとえば、風で屋根の一部が飛び、通行人にけがをさせた場合など、損害賠償責任を問われる可能性もあります。これは民法上の「不法行為責任」や「占有者責任」として処理されるケースがあり、たとえ相続放棄をしていても完全に免責されるとは限りません。
3. 引き継いだ空き家を放置することで発生しうる主な問題点
空き家は定期的に人の手が入らないと急速に劣化します。建物の劣化だけではなく、社会的・法的にも多くの問題を引き起こします。
3-1. 周辺住民との摩擦や苦情の要因になりうる
放置された空き家は、雑草の繁茂、ゴミの不法投棄、害獣・害虫の発生といった問題を引き起こします。結果として、近隣住民とのトラブルや苦情の原因になります。これが自治体に通報されると、行政指導や強制的な対策が行われることもあり、費用負担が発生するケースもあります。
3-2. 定期的な管理費・修繕費などの経済的負担
空き家であっても、換気・掃除・修繕など最低限の管理が必要です。これを業者に依頼する場合、年間数十万円のコストが発生することもあります。長期間放置すればするほど、雨漏りやシロアリ被害などの修繕費もかさみます。
3-3. 経年劣化による資産価値の減少リスク
建物は人が住んでこそ維持されるものであり、空き家は使用されないことで急速に傷みます。壁紙や床の腐食、配管の劣化、基礎の沈下などが発生し、最終的には資産価値がゼロに近づきます。
3-4. 不動産税制上の継続的な納税義務
所有している限り、たとえ利用していなくても固定資産税と都市計画税は毎年発生します。納税通知は通常1月1日時点の登記名義人に送付され、支払い義務が発生します。
3-5. 「特定空家」指定による税負担の増加リスク
市町村は、管理不全とみなした空き家を「特定空家」に指定することができます。この指定を受けると、それまで適用されていた住宅用地特例(課税評価額の1/6軽減)が外され、固定資産税が最大6倍に跳ね上がることもあります。さらに、改善命令や最悪の場合は行政代執行による解体もありえます。
4. 評価額のある空き家をどう活用するかの選択肢
空き家にある程度の資産価値がある場合、それを活かす方法は複数あります。売却、賃貸、自身での居住など、用途に応じた活用を検討することが重要です。
4-1. 3年以内の譲渡による特例活用を検討
相続開始から3年以内に空き家を売却した場合、「被相続人居住用家屋等の譲渡所得の3,000万円控除特例」が適用される可能性があります。この特例を利用すれば、売却益が3,000万円まで非課税になるため、大きな節税効果が見込めます。条件としては、被相続人が一人暮らしであったことや、売却までの間に誰も居住していなかったことなどがあります。
4-2. 賃貸物件として運用する可能性
立地や建物の状態が良ければ、空き家をリフォームして賃貸物件として活用する選択肢もあります。地域によっては需要が見込め、継続的な家賃収入を得ることも可能です。収益性を見積もるためには、近隣の家賃相場や修繕費用、管理会社への委託料などを事前に試算することが必要です。
4-3. 自らの住居として活かす場合
実家に戻って住む、あるいは二拠点生活やテレワーク拠点として活用するという方法もあります。また、居住することで「小規模宅地等の特例」など相続税の優遇措置が適用される場合もあるため、節税面でも有利に働くことがあります。
5. 利用価値が乏しい空き家への対応策
空き家が老朽化していて利用価値がほとんどない場合は、費用をかけてでも処分や解体を検討する必要があります。
5-1. 解体後の土地利用計画を立てる
建物が老朽化し、倒壊や災害のリスクが高い場合は、解体することで安全性が確保され、土地の活用方法も広がります。解体後は駐車場、資材置場、太陽光発電用地などへの転用も検討できます。解体費用は建物の構造や地域によって異なりますが、数十万円〜百万円を見込んでおくとよいでしょう。
5-2. 公的機関や法人等への無償譲渡を検討
自治体やNPO法人、社会福祉法人などに無償で譲渡するケースもあります。ただし、相手方が解体や修繕の費用を負担する必要があるため、必ずしも引き取り手が見つかるとは限りません。地域おこし事業や空き家バンクとの連携を図ることも一つの方法です。
5-3. 隣接地所有者への譲渡を模索する
隣地所有者にとっては敷地の拡張や利便性の向上につながるため、交渉の余地があります。特に都市部では隣地との一体活用で資産価値が上がる可能性があり、スムーズに譲渡が進むこともあります。
5-4. 国庫帰属制度を利用した処分方法
令和5年(2023年)より施行された「相続土地国庫帰属制度」を利用すれば、不要な土地を国に引き取ってもらうことができます。ただし、建物がある場合は事前に解体が必要であり、また管理費相当額として負担金(原則20万円)が必要です。さらに、土壌汚染や境界未確定の土地は対象外とされます。
6. 空き家の相続登記を怠るとどうなるか
2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。これまで「登記しなくても問題ない」と考えられていた慣習が一変し、法的リスクが明確になったのです。
6-1. 所有権移転のための登記手続きとは
相続登記は法務局で行います。申請には登記申請書、必要書類一式、登録免許税を納付したことを証する書面などが必要です。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書が添付されるのが一般的です。近年はオンライン申請にも対応しており、司法書士に依頼せず自身で行う方も増えています。
6-2. 登記に必要となる書類一覧
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本と住民票
- 固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書(または法定相続情報一覧図)
- 登記申請書
6-3. 相続登記に関連する主な費用
登録免許税は不動産評価額の0.4%です。司法書士に依頼する場合、報酬として5万円〜10万円程度が相場ですが、案件の複雑さにより変動します。自身で手続きを行えば費用を抑えることも可能です。
7. 空き家は早期に処分することで得られるメリットがある
空き家の処分は後回しにすると費用・労力ともに大きくなり、相続人間のトラブルの原因にもなります。早期に対処すれば、税金の負担軽減や資産の有効活用が可能となります。
7-1. 相続関連の手続きを円滑にまとめて進める方法
司法書士・税理士・不動産業者などと連携することで、相続登記から売却・活用までを一括で進める「ワンストップサービス」が利用できます。相続人が複数いる場合にも情報共有や役割分担がしやすく、手続きを迅速かつ円滑に進めることができます。専門家に相談することで、法律や税務のリスクも軽減され、安心して相続処理が行える環境が整います。